雷に関係する言葉はたくさんあります。落雷・雷鳴・雷電・電光・側撃雷など気象予報士試験を受けるとなると一つ一つ整理しておきたいところ。
雷電とは雷鳴+電光
雷電とは雷鳴という音が聞こえる状態と電光という光が見える状態を合わせたものを言います。逆を言えば、雷の音だけ聞こえて光が見えなかったのなら「雷鳴」で雷の音は聞こえなかったけど光ったのが見えたのなら「雷光」となります。
国際式天気記号の雷の表記
国際式天気記号で雷は下の画像のようになります。

ギザギザしているところがいかにも雷を想像させますね。
面白いのがこの雷電の天気記号は「雷鳴」と「電光」の天気記号が合わさってできている点です。
「雷鳴」と「電光」の天気記号をされぞれ見てみましょう。

視覚的にギザギザしており、電光を示します。

電光は見えなかったけど雷鳴だけする状態です。
雷電の天気記号を分解したような天気記号ですよね。電光と雷鳴が合わさってはじめて雷電になることがよくわかる記号のデザインになってます。
気象庁は電光のみは雷として認めない?!
気象庁の資料「気象観測の手引き」の60ページを見ると、
- 雷電:雷光と雷鳴がある現象
- 雷鳴:電光に伴う音響現象
とあり、電光に対する説明がありません。ひょっとすると気象庁は電光のみの観測では雷電として認めないということなのだろうか。理解できるようになったらまた記述します。
雷を作るための3要素
雷は次の3要素で生まれる気象現象です。
①材料
積乱雲
氷の粒や雨粒
②環境
積乱雲が発達しやすい不安定な大気
③きっかけ
雲内や雲と地上の間の電位差が限界に達し、空気の「絶縁破壊」が起こること
※「絶縁破壊」とは、本来電気を通しにくい絶縁体が、限界値以上の大きな電圧により電流を流してしまう現象のことです。雷の場合は、普段は電気を通さない空気が、大きな電圧(電界)の発生により、一気に電気を通すようになります。この瞬間に「放電」が起こり、雷が発生します。
雷が発生するためには積乱雲が必要
雷が発生するメカニズムは、積乱雲の中にある強い上昇気流で氷の粒などがぶつかり合い静電気が発生し、その電気の差が大きくなって放電することで起こります。氷の粒がよくぶつかるのは気流が荒れている積乱雲の中になります。
氷の粒がぶつかり合うことで積乱雲の中に電気が蓄積されていき、積乱雲自体が巨大な乾電池のようになります。やがて積乱雲自体に電気が溜まりすぎると、空気の絶縁力を超えて絶縁破壊を起こして雷として放電されます。



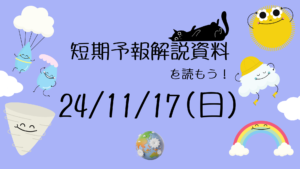
コメント